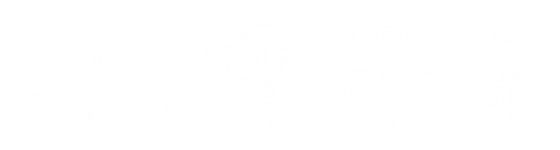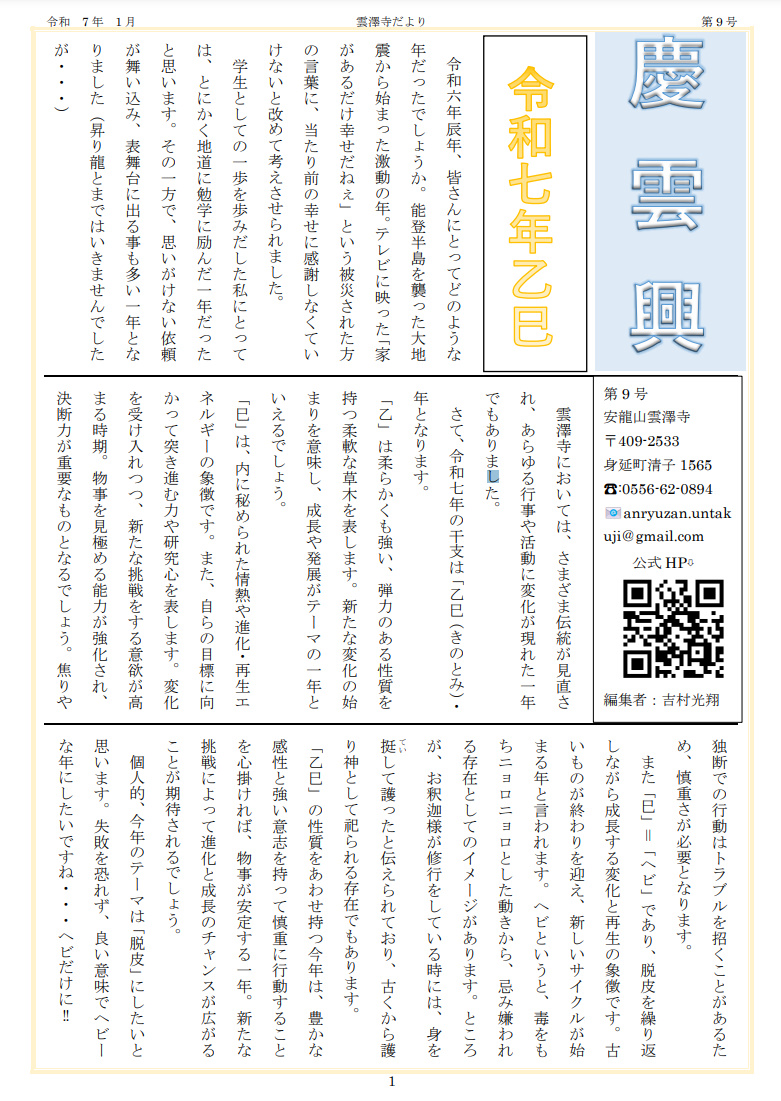令和六年辰年、皆さんにとってどのような年だったでしょうか。
能登半島を襲った大地震から始まった激動の年。
テレビに映った「家があるだけ幸せだねぇ」という被災された方の言葉に、当たり前の幸せに感謝しなくていけないと改めて考えさせられました。
学生としての一歩を歩みだした私にとっては、とにかく地道に勉学に励んだ一年だったと思います。その一方で、思いがけない依頼が舞い込み、表舞台に出る事も多い一年となりました(昇り龍とまではいきませんでしたが・・・)
雲澤寺においては、さまざま伝統が見直され、あらゆる行事や活動に変化が現れた一年でもありました。
さて、令和七年の干支は「乙巳(きのとみ)・年となります。
「乙」は柔らかくも強い、弾力のある性質を持つ柔軟な草木を表します。新たな変化の始まりを意味し、成長や発展がテーマの一年といえるでしょう。
「巳」は、内に秘められた情熱や進化・再生エネルギーの象徴です。また、自らの目標に向かって突き進む力や研究心を表します。変化を受け入れつつ、新たな挑戦をする意欲が高まる時期。物事を見極める能力が強化され、決断力が重要なものとなるでしょう。焦りや独断での行動はトラブルを招くことがあるため、慎重さが必要となります。
また「巳」=「ヘビ」であり、脱皮を繰り返しながら成長する変化と再生の象徴です。古いものが終わりを迎え、新しいサイクルが始まる年と言われます。ヘビというと、毒をもちニョロニョロとした動きから、忌み嫌われる存在としてのイメージがあります。ところが、お釈迦様が修行をしている時には、身を挺(てい)して護ったと伝えられており、古くから護り神として祀られる存在でもあります。
「乙巳」の性質をあわせ持つ今年は、豊かな感性と強い意志を持って慎重に行動することを心掛ければ、物事が安定する一年。新たな挑戦によって進化と成長のチャンスが広がることが期待されるでしょう。
個人的、今年のテーマは「脱皮」にしたいと思います。失敗を恐れず、良い意味でヘビーな年にしたいですね・・・ヘビだけに‼
「よいお年をお迎えください!」
「明けましておめでとうございます!」
何気ない会話の中に添えられる年末年始の挨拶に、清々しさを感じるこの頃です。相手の幸せを祈る言葉が自然に交わされるこの季節、私たちの心には特別な温もりがあるような気がします。
お正月はお盆と並んで、日本で古来より伝わる宗教観が表れる特別な行事だと思います。ところが、「宗教」という言葉を聞くと、オウム真理教や統一教会の騒動などの影響からか、警戒心やうさん臭さを感じる人も多いのではないでしょうか。そのため、自分には特定の宗教がないと考え「無宗教」と公言する人も少なくありません。
実際には、多くの人が何らかの宗教的な行事を日常生活の中で行っています。それは無宗教というより、宗教的な習慣が生活に深く溶けこみ、当たり前すぎて意識されなくなっているだけなのかもしれません。祈りのある場所には必ず宗教が存在しています。
たとえば、年末には多くの家庭でせっせと大掃除をし、門松やお飾りを用意して、新年に幸せをもたらす神様「年神様」を迎える準備をします。昔は各家にかまどがあり、年末には「釜締め」という風習がありました。これは、かまどや台所を守る火の神様に感謝を捧げ、火を落としてかまどを閉じる行為です。そして、お正月の火を使わない期間に食べるよう、準備されたのが「おせち料理」でした。
おせちは年神様に供えられ、お供えしたものをいただく事で、神様の恵みを授かると考えられてきました。エビには「元気で長生きできますように」、黒豆には「まじめに働き、健康に暮らせますように」という意味が込められているように、すべての料理に「~ますように」という祈りが込められています。
また、子どもたちにとって最高の楽しみであるお年玉は、かつては餅だったと伝えられています。神様が宿るとされる鏡餅には、神様の魂や力が宿り、それを切り分けることで子どもの成長や健康を祈ったそうです。つまり「お年玉」=「お年魂」だったのです。
多くの人が自然に他者の平和と健康を祈ることができる年末年始。ただの伝統や風習としてだけでなく、ささやかな祈りがこめられている事を、次の世代へと伝えていくことも大切ではないでしょうか。